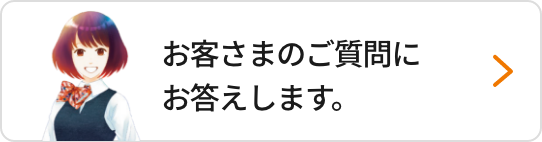相続関連用語集
| 相続人 | 死亡した人の財産(積極財産と消極財産)を承継する人をいいます。 |
|---|---|
| 遺言執行者 | 遺言の内容を実現する為に選任された者で、相続人の代理人となる人をいいます。遺言者が遺言のなかで指定する場合と、家庭裁判所で選任される場合とがあります。遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分をしたり、遺言の執行を妨害したりすることは禁止されています。 |
| 相続財産管理人 | 相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続するものがいなくなった場合も含まれる。)には、家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の管理人を選任します。 相続財産管理人は、被相続人(お亡くなりになった方)の債務者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後の残った財産を国庫に帰属させることになります。なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故にあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。 |
| 相続放棄 | 相続人は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述することができます。相続放棄した者は、その相続に関しては、初めから相続人ではないことになります。なお、相続放棄した者に子があっても代襲相続にはなりません。 |
| 特別縁故者 |
相続人が不存在の場合、(相続人のあることが明らかでない場合)、相続財産はそれ自体が法人(相続財産法人)とされ、相続財産管理人による管理が開始されます。 相続人の不存在が確定した場合、遺産を国庫に帰属させるよりも、被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻や事実上の養子など)、療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者(「特別縁故者」といいます)に相続財産分与することとしました。 相続人不存在の確定後(最後の相続人捜索の公告期間満了)3ヶ月以内に、特別縁故者として財産分与を受けようとする者が家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所より特別縁故者として相当と認められたときは、残存財産の全部または一部がこの特別縁故者に分与されることになります。 |
| 公正証書遺言 | 2人以上の証人を得て、遺言人が公証人に遺言の趣旨を口授(もしくは手話通訳、自書)することにより作成される遺言です。公証人が作成することから、遺言の存在と内容が明確であるとのたてまえから、検認の必要はありません。 |
| 自筆証書遺言 |
遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書・押印することによって成立する遺言です。 遺言者は財産目録に限り、パソコンによる作成、登記事項証明書や預金通帳のコピーの添付が可能です。但し、財産目録の全てのページに遺言者の署名押印が必要になります。証人・立会人は不要ですが、偽造・変造されたり、滅失したりするおそれがあります。自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所の検認が必要です。 |
| 検認 | 相続人、遺言執行者などが家庭裁判所に赴き、立会いのもとで、遺言書の状態などを調査・確認することをいいます。検認は、遺言書の偽造・変造・隠匿等を防止するために行われる検証・証拠保全手続であり、遺言書の真偽を判定するものではありません。従って、適法でない遺言書については、検認がなされたからといって有効になるものではありません。封入されている遺言書は、家庭裁判所において相続人、遺言執行者等が立会のもと開封しなければなりません。 |
| 受遺者 | 遺言により遺贈を受ける人を受遺者といいます。受遺者には相続人のみならず相続人以外の者や法人でもなれます。 |
| 遺贈 |
遺言者が自分の財産を特定の人に無償で与える行為を遺贈といい、包括遺贈による場合と、特定遺贈による場合があります。 遺贈を受ける人を受遺者といい、受遺者には相続人だけでなく、相続人以外の者や、法人でもなれます。 |
| 遺留分 | 遺留分とは、被相続人の一定の近親者(兄弟姉妹を除く法定相続人)に留保された相続財産の一定割合のことをいいます。遺言者は、遺言により自分の財産を自由に処分できますが、兄弟姉妹を除く相続人には一定割合の相続財産を留保する必要があります。 |
| 遺産分割協議 | 共同相続人が、相続人間で、どの相続財産を誰が相続するかを協議することをいいます。また、遺産分割協議の内容を文書にしたものを遺産分割協議書といいます。共同相続人全員でなされていることが法律上の要件です。 |